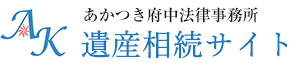- ホーム
- >
- 遺留分
遺留分
1 遺留分とは
被相続人は、遺言によって自由に自己の財産を処分できるのが原則ですが、遺族の生活保障などの理由により、相続財産のうち、遺言によっても侵害できない最低限度の取り分が法律上保障されています。この取り分のことを、遺留分といいます。
2 遺留分権者及びその割合
遺留分権を有する相続人は、被相続人の配偶者、子及び直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分権がありません。
相続人全体の遺留分の割合は、相続人が誰かにより異なります。
各相続人の個別的遺留分の割合は、これを各自の法定相続分で分けたものです。
① 直系尊属(両親等)のみが相続人の場合
被相続人の財産の3分の1
② その他の場合
被相続人の財産の2分の1
たとえば、配偶者と子2人が相続人である場合の子1人の遺留分は、全体の遺留分2分の1に、その子の法定相続分4分の1を乗じた、8分の1になります。
3 遺留分の計算方法
① 遺留分算定の基礎となる財産
1)被相続人が相続開始時に有していた財産の価額 に
2)被相続人が贈与した財産の価額を加え
3)被相続人が負担していた債務の全額を控除した金額を基礎として、計算します(民法第1029条第1項)。
2)について、原則として相続開始以前1年間にした贈与が加算の対象となりますが、被相続人と受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年以上前にした贈与も加算の対象となります(民法第1030条)。
ただし、相続人に対して、生計の資本となるような特別な贈与(これを「特別受益」といいます。)をした場合には、その贈与が1年以上前のものであっても、また、遺留分権利者に損害を加えることを知らなくても、原則として加算の対象となります(最高裁平成10年3月24日判決)。
なお、被相続人からの生前贈与が「特別受益」にあたる場合、被相続人の意思表示により相続分の計算上その贈与を加算しないこととされた贈与でも、遺留分の計算上は、加算されることになります(最高裁平成24年1月26日決定)。
② 遺留分算定の基礎となる財産の評価
遺留分算定の基礎となる財産は、原則として相続開始時を基準に評価されることになります。例えば、不動産は相続開始時の時価で評価されますし、生前贈与された現金も、相続開始時の貨幣価値に換算して評価されることになります。
また、時価より不相当に低い価額で売却した場合、時価と売買価額との差額を贈与とみなして、遺留分算定の基礎となる財産に加算することになります。4 いつまでに遺留分を行使する必要があるか
① 相続が開始したこと
及び
② 自己の遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から
1年以内に行使する必要があります。
もっとも、1)及び2)を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年を経過した場合は、遺留分を行使することができなくなります(民法第1042条)。5 遺留分を行使する方法
遺留分権利者は、必ずしも裁判により権利行使しなければならないわけではなく、遺言や生前贈与により財産を取得した者に対し、遺留分減殺請求の意思表示をすれば足ります。もっとも、意思表示を行った証拠を残すために、配達証明付内容証明郵便で行うべきです。
意思表示を受けた相手方が応じるのであれば、協議による解決を目指します。
6 遺留分の協議が整わない場合
裁判外の意思表示によっても協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停を起こすことになります(家事事件手続法第244条)。調停を経ずにいきなり訴訟手続で解決することは、原則としてできません(家事事件手続法第257条)。
7 訴訟で解決する場合
遺留分減殺請求の調停が成立しない場合には、遺留分減殺請求の効果として自己に所有権や持分権が帰属したとして民事訴訟を提起することになります。
8 請求前に財産を譲渡してしまった場合
遺留分減殺の対象となる遺贈や贈与により財産を取得した者が、遺留分減殺請求前に、当該財産を第三者に譲渡した場合、当該遺贈や贈与に対して遺留分減殺請求をするには、当該第三者に対し請求して遺贈・贈与された現物を回復するのではなく、受遺者・受贈者に対し目的物の譲渡時の評価額の弁償を請求するのが原則です(民法第1040条第1項本文)。
ただし、当該第三者が遺留分権利者に損害を与えることを知っていたときは、その者に対しても遺留分減殺請求を行うことができます(民法第1040条第1項ただし書)。
9 請求後に譲渡してしまった場合
遺留分減殺請求を受けた受遺者・受贈者が、その後に目的物を第三者に対し譲渡してしまった場合、当該第三者に対して更に遺留分減殺請求をすることはできません(最高裁昭和35年7月19日判決)。
また、例えば目的物が不動産である場合、遺留分減殺請求により所有権を取得した旨の登記をまだしていない場合には、当該第三者に対して所有権の取得を主張できません。
この場合には、受贈者・受遺者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます(大阪高等裁判所昭和49年12月19日判決)。
10 遺留分の放棄
相続開始後においては、遺留分権者は自由に遺留分を放棄できますが、相続開始前においては、家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第1043条第1項)。
なお、家庭裁判所は、①遺留分の放棄が遺留分権者の自由意思に基づき、②遺留分を放棄することに合理的な理由と必要性があり、③遺留分放棄と引き換えに贈与等の代償を受けている場合には、遺留分の放棄を許可します。
11 遺留分の請求を受けた場合
遺留分減殺請求を受けた場合、どの財産から遺留分権者の遺留分を確保するかが問題となります。
この点、①遺贈と贈与があるときは、まず遺贈から減殺する、②複数の遺贈があるときは、各遺贈の目的額に応じて割合的に減殺する、③複数の贈与があるときは、後の贈与から前の贈与へ順番に減殺する、と定められています(民法第1033条~第1035条)。
遺言実務で広く定着している「相続させる」遺言については、遺贈と同順位で減殺すべきとされています。
なお、遺留分権者が、複数の対象財産の中から特定の財産を選択して減殺することは認められていません。
そのうえで、ある遺贈や贈与が減殺された場合、その効力が遺留分を侵害する限度で否定され、遺留分権者がその範囲で遺贈又は贈与の目的物を取得するのが原則です(最高裁昭和41年7月14日判決)。
ただし、減殺請求を受けた者は、当該遺贈又は贈与の目的物の価額を弁償することにより、現物返還を免れることもできます(民法第1041条)。
しかし、実際に弁償すべき価額を計算することは極めて困難なので、遺留分減殺請求を受けた場合に、現物返還を免れたい場合には、価額弁償の意思表示と共に、裁判所に対し、弁償すべき額が判決により確定されたときは速やかに支払う旨の主張をしておけばよいことになっています(最高裁平成9年2月25日判決)。
12 揉める場合
例えば、遺留分を侵害する内容の遺言があり、遺留分減殺請求の結果、価格弁償しなければ不動産が共有状態になってしまうものの、価格弁償するだけの資金がない、という場合があります。当分の間不動産の共有状態が続くことになり、不動産の管理や処分に支障を来たすことになりますので、このような事態は事前の対策により極力避けるべきです。
また、同族会社の事業承継の際に、当該会社の株式が相続財産の中で大きな割合を占めているような場合、例えば長男に会社を継がせるため全株式を長男に相続させたいが、それでは他の相続人の遺留分を侵害してしまう、というのもよくあるケースです。
13 紛争を生じさせないようにする方法
遺留分侵害の問題を未然に防ぐためには、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成するのが確実な方法です。
もっとも、従来の経緯から、どうしても特定の相続人に遺産を残したくないという場合には、法的効力はありませんが、遺留分減殺請求を差し控えるよう求める付言事項を遺言書に記載しておくという方法があります。
なお、特定の相続人に遺産を残したくない理由が、当該相続人から虐待を受けたとか、重大な侮辱を受けたというような場合は、生前に推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができ(民法第892条)、これが認められれば、その者は相続人の地位を失う結果、遺留分も当然持たないことになります。
14 遺留分に関する民法の特例
「私は会社を経営していますが、そろそろ引退して、長男に会社を継がせたいと考えています。遺留分に関する民法の特例があると聞いたのですが、それはどのようなものでしょうか。」
経営者の財産の大部分が自社株式や事業用資産である場合に、後継者となる相続人に自社株式や事業用資産を生前贈与や遺言により承継させることにしても、他の相続人から遺留分減殺請求されてしまうと、自社株式や事業用資産が分散し、事業の継続が難しくなります。
そこで、中小企業の事業承継が円滑に行えるようにするため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)が民法の遺留分に関する特例を定めています。
① 特例の内容
経営者が後継者に自社株式等を生前贈与した場合に、民法上は、遺留分の計算の基礎となる財産について、相続開始時の財産に、被相続人が生前贈与した財産の価額を加えることになりますが(民法第1029条第1項)、経営承継円滑化法は、これに対し、1)除外特例、2)固定特例、という2つの特例を設けています。
1)除外特例
相続人となるべき者全員(ただし、遺留分権がない兄弟姉妹を除きます。)が、経営者の生前に合意することにより、遺留分の計算の基礎となる財産につき、被相続人が生前贈与した自社株式等を加えず、遺留分減殺の対象ともしないことができます。
2)固定特例
相続人となるべき者全員が、経営者の生前に合意することにより、被相続人が生前贈与した自社株式等の価額を遺留分の計算の基礎となる財産に加える際に、その価額を当該合意時における価額(ただし相当な価額であることにつき弁護士等の証明を要します。)に固定することができます。
※ なお、①②の特例共に、従来は相続人となるべき者に自社株式等を生前贈与した場合しか適用できませんでしたが、平成28年4月施行の改正経営承継円滑化法により、相続人となるべき者以外の者に生前贈与した場合にも適用できることになりました。
その場合は、相続人となるべき者全員と贈与を受けた後継者とで合意をすることになります。
② 特例を受けるための手続
いずれの特例も、合意後1か月以内に経済産業大臣への確認申請を行い、確認を受けてから1か月以内に家庭裁判所に遺留分算定にかかる合意の許可申立てをしなければなりません。
③ 留意点
事業承継円滑化法は、上記①②の遺留分に関する特例以外にも、相続税・贈与税の納税猶予の特例(いわゆる事業承継税制)や、金融支援制度などの内容も含むものです。この点につきましては、税理士などの専門家にご相談ください。
遺留分

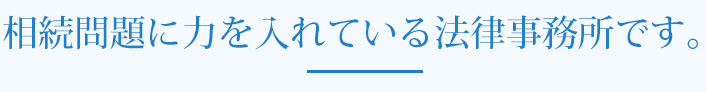
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

代表弁護士 金田 真明
![]()
東京都府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル3階
経歴
富山県高岡市出身。
慶應義塾大学法学部法律学科、関西学院大学司法研究科卒業。
司法修習修了後、東京都日本橋にある第一中央法律事務所で勤務。
同事務所では、企業の再生や労務問題等、企業にまつわる様々な業務に携わりました。
2011年1月11日に、あかつき府中法律事務所を設立
主な対応エリア
立川市/八王子市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/武蔵村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/
多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市/瑞穂町/日の出町/檜原村/奥多摩町の多摩地区/その他23区および神奈川県(南武線、小田急線沿線地域)埼玉県・山梨県など。
COPYRIGHT©あかつき府中法律事務所ALL RIGHTS RESERVED.