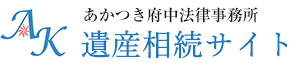- ホーム
- >
- 遺言書作成
遺言書作成
1 遺言とは何か
遺言を作成することにより、法定相続分ではない割合で遺産を分けたり、相続人以外の人に遺財産を分けたりすることが可能になります。 遺言がなければ、法律で定まっている法定相続分により遺産を分けられてしまいます。
2 遺言書を作成した方が良い場合
① 法定相続分とは異なる割合で遺産を分けたい場合
■ 事例
「Aさんには、3人の子どもがいます。Aさんの夫は10年前に亡くなっています。長男Bさんと次男Cさんは遠方に住んでいて、近所に住む長女のD子さんが介護の世話をしてくれています。Aさんとしては、面倒を見てくれているD子さんに他の兄弟よりも多くの遺産を渡そうとしています。」
☆ 遺言書を作成することでどうなるか
法定相続分は3人の子ども達で3分の1ずつです。遺言書を作成しないと、Aさんの財産はBさん、Cさん、D子さん3分の1ずつで分けることになります。 遺言書を作成することで、法定相続分である3分の1よりも多くの財産をD子さんに残すことができます。
② 特定の遺産を特定の相続人に分けたい場合
■ 事例 Aさんには、妻と2人の子どもがいます。妻のB子さんには預貯金を、長男のCさんには自宅の土地建物を残そうと考えていますが、長女のD子さんはAさんと仲が悪く、D子さんには遺産を残したくないと考えています。
☆ 遺言書を作成することでどうなるか
法定相続分は妻が2分の1、2人の子どもが各4分の1ずつです。遺言書を作成しないと、B子さん、Cさん、D子さんの間で、具体的にどの財産をどのように分けるかについて遺産分割協議をする必要があり、協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判という手続きの中で解決せざるを得なくなります。 遺言書を作成することで、遺産分割協議をすることなく、どの財産を誰に 分けるかを決めることができます。
③ 相続人以外の人に遺産を分けたい場合
■ 事例 Aさんには、妻と子どもがいますが、妻のB子さんと子どものCさんは10年以上前に家を出て、それ以来ほとんど連絡を取っていません。Aさんは、5年ほど前にD子さんと知り合いましたが、D子さんが身の回りの世話をよくやってくれるので、D子さんに遺産を残したいと考えています。
☆ 遺言書を作成することでどうなるか
遺言書を作成しなければ、法定相続人の間で遺産を分けることになります。遺言書を作成することで、法定相続人ではないD子さんに遺産を残すことができます
④ 残された配偶者の扶養などの負担を条件として、遺産を相続させたい場合
■ 事例 Aさんには、妻と2人の子どもがいます。妻のB子さんは、足腰が悪く、日常生活に支障が出ています。長男のCさんは、既に家を出て事業を成功させており、多忙です。長女のD子さんは、B子さんと一緒に暮らしていますが、経済力がありません。Aさんは、D子さんに、B子さんの介護をしてもらうかわりに、財産を残そうと考えています
☆ 遺言書を作成することでどうなるか 遺言書を作成しなければ、B子さん、Cさん、D子さんの間で遺産分割協議をしなければなりません。 遺言を作成することで、自分の死後の配偶者の生活と子の経済的基盤とを確保することができます。
3 遺言の種類
① 遺言の方式
大きく分けて普通方式(民法第967条~第975条)と特別方式(民法第976条~第984条)の2種類があります。
特別方式は、死期が急に迫っている場合など特殊な状況下にある場合に例外的に作成される方法であり、通常は普通方式が用いられます。
② 普通方式
1)自筆証書遺言
2)公正証書遺言
3)秘密証書遺言
以上の3つがありますが、実際に利用されている遺言の大多数は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
4 自筆証書遺言の要件
① 遺言書の全文と作成日付、名前を自ら手書き
② 印鑑を押すことが必要です。
5 自筆証書遺言の利点と弱点
① 自筆証書遺言の利点~費用をかけずに作成できること
公正証書遺言では公証人の手数料が必要ですが、自筆証書遺言なら自分一人でも作成できるので費用がかかりません。
② 自筆証書遺言の弱点
1)方式の不備や内容の不備により無効とされるおそれがあること
公証人が作成してくれる公正証書遺言に比べて、自分で法律上定められた方式を全て満たした遺言書を作成することは難しく、無効とされるおそれが高いといえます。
2)遺言が偽造・変造されたり隠匿されたりする可能性があること
公正証書遺言の場合には、遺言が作成された時点で遺言は公証役場において厳重に保管されますが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認手続を経るまでは、偽造・変造されたり、隠匿されたりする可能性があります。
3)家庭裁判所による検認の手続きを経る必要があること
遺言書を保管している者や、遺言書を発見したものは、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求しなければなりません。
4)自書できない者は作成できないこと
全文、日付、署名を自書することが自筆証書遺言の要件となっています(民法第968条第1項)。公正証書遺言なら、遺言の内容を口頭で説明できれば足ります。
6 自筆証書遺言が無効となった例
① 他人の添え手により遺言した場合に無効となった例
自筆証書遺言は全文を自書することが必要ですが、病気等により自書することができない者が他人の添え手により遺言した場合で、添え手の程度が遺言者の手を用紙の正しい位置に導いたり、筆記を容易にする支えとなったりという程度を超えて、添え手をした他人の意思が介在したものとして無効とされた例(最高裁昭和62年10月8日判決)。
② 日付の特定を欠くとして無効とされた例
日付を「〇年〇月吉日」と書いた例(最高裁昭和52年11月29日判決) ③ 文書と封筒の一体性が認められないとして無効とされた例 遺言書に署名押印がなく、既に家庭裁判所の検認時に開封されていた封筒には署名押印があった例(東京高等裁判所平成18年10月25日判決)
7 自筆証書遺言を訂正する場合
自筆証書遺言を訂正する場合は、訂正箇所に印を押し、欄外に「この行〇字加入(〇字削除)」等と書いたうえ、その部分に署名しなければなりません(民法第968条第2項)。 この加除変更の方式を守らなかった場合は、遺言書が無効になるのではなく、その加除変更がなかったことになります。
8 検認とは
公正証書遺言以外の遺言の場合は、家庭裁判所の検認を経なければなりません。
検認とは、遺言書の状態を確認して、それ以降の偽造・変造を防ぐための手続きです。
なお、遺言書の法的効果を判断する手続ではないため、検認を経た遺言につき、遺言無効確認の訴えを起こすこともできます。
遺言書を保管していた者やこれを発見した者は、遅滞なく、遺言を家庭裁判所に提出して検認手続を請求しなければなりません。
検認が請求されると、家庭裁判所は相続人やその代理人に対し、検認をする期日の通知を行い、検認に立ち会う機会を与えます。
検認手続では、家庭裁判所は、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、検認調書を作成します(家事事件手続法第211条、家事事件手続規則第113条~第114条)。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又は代理人の立会いのもと開封しなければなりません。
公正証書遺言の場合は、検認を経る必要はありません。
9 遺言を隠したり破棄したりした場合
遺言を発見したのに、家庭裁判所への検認請求をしなかったり、検認を経ない遺言書に従って名義変更等の遺言の内容の実現を行ったり封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には、5万円以下の過料を課されます。
また、より重大な効果として、遺言書を隠したり、破棄したりした場合は、法律上当然に相続人から除外されます。
10 公正証書遺言の要件
公正証書遺言は、公証人が公正証書という形で作成する遺言です。 公正証書遺言を作成するためには以下の要件を満たす必要があります。
① 証人2人以上の立会いの下
② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ
③ 公証人がその内容を公正証書としてまとめたものに、遺言者、証人及び公証人が署名押印すること
です。
11 証人になることができない人
① 未成年者
② 相続人・受遺者になる方及びこれらの配偶者・直系血族
③ 公証人の配偶者・四親等内の親族、公証役場の書記・使用人
※ 証人に心当たりがない場合は、公証役場で紹介してもらえます(ただし、若干の謝礼を支払う必要があります。具体的には、公証人の指示に従ってください)。
12 公正証書遺言の利点と弱点
① 公正証書遺言の利点
1)方式の不備、内容の不備により無効とされるおそれが小さいこと
2)家庭裁判所での検認が不要であること
3)自書できない方でも作成できること
4)遺言書が公証役場に保管されるので、偽造・変造のおそれがないこと
② 公正証書遺言の問題点と評価
1)公証人の手数料がかかること ⇔公証人の手数料は、原則として、遺言により相続させ又遺贈する財産の価額と相続人等の数を基準にした、全国一律の金額です。自筆証書遺言を作成して遺言無効確認の訴えなどでトラブルを招くことを考えれば、公証人に適正な手数料を支払ってトラブルを未然に防いだ方が合理的です。
2)証人2名の立会いを要すること ⇔公正証書遺言を作成するためには、2名以上の証人の立会いが必要ですが、証人になってくれる人に心当たりがない場合、公証役場で紹介してもらえます。したがって、この点はほとんどデメリットではありません。
【結論】 自筆証書遺言は、全文と作成日付、署名を自書することなど、厳格な方式を守らなければならず、無効とされるリスクが高いうえ、家庭裁判所での検認手続を要します。 それに比べ、公正証書遺言なら、無効とされるリスクが極めて低く、検認も 必要ありません。遺言を作成する場合は、公正証書遺言がおすすめです。
13 公証役場とはどういうところか
公証役場とは、公証人が公正証書の作成等の業務を行う官公庁です。公証人は、主に元裁判官や元検察官が任命されます。このような法律の専門家が作成するため、公正証書遺言は信用性が高いものとされ、家庭裁判所での検認手続が不要とされているわけです。
14 遺言能力とは
遺言は遺言者が判断能力ある状態で作成されたことが必要で、この判断能力のことを遺言能力といいます。
遺言能力は、次のような要素から有無が判定されます。
① 年齢・主治医の判断
主治医が遺言作成当時にカルテや診断書に自己の財産を管理処分する能力がある旨記載していた場合には、遺言能力が認められやすいといえます。
なお、高齢であること自体で遺言能力が否定されることにはなりませんが、高齢の方が遺言書を作成する場合は、知能検査を実施してもらい、診断書を作成してもらうなど、遺言能力をめぐる争いが起きにくいように対策を取ることが重要です。
② 遺言の内容が単純かどうか
全財産を長男Aさんに相続させるといった単純な内容の遺言は遺言能力が肯定されやすいといえます。
一方、それぞれの財産を細かく、どこどこの不動産はAさん、○○銀行の預金のうち幾ら幾らと、○○証券の〇〇の株式はBさん・・・といった複雑で、何枚にも及ぶな内容の遺言は、ある程度の判断能力がなければ無効とされやすいといえます。
③ 遺言前後の状況 遺言前後の生活状況や言動なども、遺言能力の有無を判断する重要な要素となります。
たとえば、医師による認知症との診断書がある場合でも、普段は意識が比較的はっきりしており、遺言作成後に新聞を読むことができたことなどから、遺言能力を認めているケースもあります(和歌山地方裁判所平成6年1月21日判決)。
④ 遺言を作成する経緯等に不自然な点がないかどうか
遺言を作成する経緯で、遺言により利益を受ける者が主体的に動いている場合や、遺言作成時に遺言者が積極的な意思表明をしていない場合などには、遺言能力が否定されやすいといえます。
15 遺言能力が否定された例
① 遺言直前の異常な言動や、遺言をした翌日に遺言をしたことを思い出せなかったこと、従来の経緯から親族でもない第三者に遺贈する動機が乏しいことから、公正証書遺言が無効とされた(名古屋高等裁判所平成5年6月29日判決)。
② 医師の鑑定や知能検査の結果から遺言同時高度の認知症にあり、しかも遺言の内容が複雑であることから、公正証書遺言が無効とされた(東京地方裁判所平成12年3月16日判決)。
id=""
16 判断能力が不十分な人による遺言
判断能力を常に欠いている方について、ご家族などの請求により、家庭裁判所によって後見開始の審判をされることがあり、この審判を受けた方を成年被後見人といいます(民法第7条~第8条)。
しかし、判断能力は常に一定ではなく、成年被後見人の方も、遺言能力を一時回復することがあります。 そのような場合には、2人以上の医師に立ち会ってもらい、遺言をする時において遺言能力を欠いている状態ではなかった旨を遺言書に付記してもらうことにより、遺言を残すことができます(民法第973条)。
なお、後見人(被後見人を代理して法律行為を行う者)が直系血族、配偶者又は兄弟姉妹である場合を除き、後見人又はその配偶者や子などの利益になるような遺言を書いた場合は、無効となります。
17 未成年者による遺言
満15歳に達しない者は、遺言をすることができませんが(民法第961条)、満15歳に達していれば、未成年者でも遺言を残すことはできます。
18 共同遺言の禁止
「私も妻も、全財産を息子に相続させようと思っています。同じような内容なので、二人の遺言を一枚の遺言書に書いてもよいですか。」
二人以上の人が同一の書面で遺言を残すことは、共同遺言として禁止されています(民法第975条)。
同一の用紙に記載されていても、切り離せば独立した遺言書となる場合には、共同遺言にはあたらないとされていますが、無効となるリスクを避けるため、ご夫妻それぞれで別々の遺言書を作成されることをお勧めします。
id=""
19 遺言に記載する事項
遺言として法的効力を有する事項は、民法その他の法律で定められている事項に限られます。
もっとも、法律で定められた事項以外の事柄を遺言書に記載することはよくあります。
例えば、遺言者の死後の葬儀や埋葬の方法について記載する場合や、相続人に対して遺留分を行使しないよう要望する場合などがあります。これらの事項は付言事項といい、法的効力はありませんが、相続人が事実上尊重することにより、遺言者の意思を実現できる可能性があります。
20 「相続させる」遺言
特定の相続人に対して特定の遺産を残したい場合、実務上、「相続させる」旨の遺言が用いられます。
具体的には、「遺言者は、遺言者が所有する下記土地を、遺言者の長男○○に相続させる。」などと記載します。
このような遺言にすることにより、その特定の遺産が、別途遺産分割協議をすることなく、相続発生と同時に、特定の相続人に承継させることができます。
21 遺贈とは何か
遺贈とは、遺言によって、自己の財産を他人に与えることをいいます。遺贈する相手は、相続人でも相続人以外の第三者でもよいのですが、相続人に対して遺産を承継する場合には、「相続させる」旨の遺言をした方が登記手続などの点で簡易ですので、遺贈の意義は、相続人以外の者に遺産を承継できるところにあります。
22 遺言を作り直したい場合
遺言は遺言者の最終意思を尊重するものなので、遺言は、遺言の方式に従い、いつでも撤回することができますし、作り直すこともできます。
撤回する場合も、作り直す場合も、遺言の方式に従っていればよいので、例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回したり作り直したりすることもできます。
23 遺言が複数ある場合
日付が異なる有効な遺言書が複数ある場合に、その複数の遺言の内容が矛盾する場合には、その矛盾する部分について前の遺言を撤回したものとみなされ、後の遺言が有効となります(民法第1023条第1項)。
一方、複数の遺言が矛盾しない場合には、全ての遺言が有効となります。
ただし、矛盾するかどうかの判断が微妙なケースもあるので、複数の遺言を作成する場合、後に作成した遺言書で、前に作成した遺言書を撤回することを記載した方が、明確になり望ましいといえます。
24 遺言無効確認の訴え
自筆証書遺言の場合は、遺言書の筆跡が本人の筆跡ではないなど、偽造された疑いがある場合があります(検認手続でも、筆跡の照合などは行われません)。
このような場合に、遺言の効力を否定するためには、裁判所に、遺言無効確認の訴えを提起するという方法があります。
なお、相続人が遺言書を偽造・変造等した場合、その者は相続人から除外されます。その場合には、裁判所に、その偽造した者が相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを提起します。
25 遺言無効の立証方法
遺言が判断能力を欠いた状態で作成された疑いがある場合も、遺言の効力を否定するには、遺言無効確認の訴えを提起することになります。
遺言無効確認の訴えにおいて、病院のカルテや検査結果、薬の処方箋、福祉施設の日誌、遺言者の言動の記録などから、遺言書を作成した前後に判断能力がなかったことを主張立証していくことになります。
公正証書遺言を作成した場合には、作成段階で公証人が判断能力の有無を確認していますので、一般的には信用性が高いのですが、判断能力を欠いた状態で作成されたものとして無効とされた裁判例が数件あります。
26 遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、遺言書の中で指定するか、家庭裁判所により選任される者をいいます。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の内容の実現に必要な一切の行為をすることができます。
一方で、遺言執行者がいる場合は、相続人は遺言の内容の実現を妨げる行為をすることができなくなります。
遺言執行者がいない場合は、各相続人が協力して遺言の内容を実現していくことになりますが、相続人預貯金の名義変更手続など、遺言の内容の実現には、面倒な手続きを伴います。面倒やトラブルを避けるためにも、遺言執行者がいた方がよいでしょう。
27 遺言執行者に適切な人は誰か
遺言執行者には、未成年者と破産者以外は誰でもなることができ、受遺者(遺言により贈与を受ける者)や相続人もなることができます。
弁護士などの法律専門家を遺言執行者として指定すれば、面倒な名義変更等の手続を効率的に進めることができます。
また、例えば不動産の遺贈の場合、原則として受遺者と遺言執行者とが共同して登記申請しなければならないところ、受遺者を遺言執行者と指定すればその者の単独申請で登記できるなど、受遺者や相続人を遺言執行者とすれば、スムーズに遺言の内容を実現できます。
一方、遺言の内容の実現には複雑な手続を要することがありますし、そもそも遺言執行者に指定・選任された者が実際に遺言執行者への就任を承諾するかは自由なので、性格や能力の面から複雑な事務手続が難しい方や、遺言執行者への就任に消極的な方を指定するのは、好ましくないといえます。事前に、遺言執行者への就任の内諾を得ておくことが必要です。
28 遺言執行者の就任から終了の職務の流れ
① 遺言執行者の就任
遺言により指定された場合も、家庭裁判所により選任された場合も、遺言執行者への就任を承諾することにより実際に就任することになります。
② 相続人の調査
③ 関係者への通知
各相続人に、遺言執行者に就職した旨を通知します。
④ 財産目録の作成・交付
被相続人の財産を調査したうえ、財産目録を作成し、各相続人に交付します。
⑤ 遺言内容の実現
不動産、預貯金等の名義変更や動産の引渡しなど、遺言内容の実現に必要な行為を行います。
⑥ 任務完了等による終了
遺言内容が実現されれば遺言執行者の任務は終了しますが、それ以外にも、死亡、辞任、解任等により職務が途中で終了することもあります。
⑦ 経過及び結果の報告等
各相続人に任務完了の通知をし、保管等していたものがあれば相続人に引き渡したうえ、任務遂行の経過及び結果を各相続人に報告します。
29 遺留分減殺請求をされた場合の遺言執行
各相続人には、遺言によっても侵害できない最低限の取り分である「遺留分」があります。
遺留分を侵害する内容の遺言も有効ですが、遺留分を侵害された者が期限内に「遺留分減殺請求」を行うと、その者の遺留分が侵害されている限度で、遺言による遺産の承継の効力が否定されます。
遺留分減殺請求をされた場合、遺留分の価額の算定など権利関係の確定には困難が伴うので、遺言執行者としては、遺留分に関する権利関係が確定するのを待ってから、名義変更等の職務を行うのが通常です。
30 遺言の付言事項とは何か
遺言書に有効に記載できる事項は法律で限定されていますが、それ以外の事項も、遺言書に記載することができ、これを付言事項といいます。
付言事項は、遺言としての効力はなく、相続人を法的に拘束しませんが、被相続人の意思を明確にすることにより、相続人が事実上付言事項に従い、被相続人の意思を実現するのに役立つ可能性があります。
例えば、特定の相続人に遺産を残さない場合に、そのような遺言を書いた理由を説明して、遺留分減殺請求を差し控えるよう付言する場合などがあります。
31 遺言で祭祀主宰者の指定を行うことの意味
祭祀主宰者とは、墓石・墓地、仏壇・位牌、家系図などを承継する者をいいます。
このような祭祀財産の承継は、遺産相続とは別のものと考えられており、被相続人が祭祀主宰者をしない場合は、慣習により祭祀主宰者を定め、それでも明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀主宰者を定めることになっています。
遺言で祭祀主宰者を指定しておくことにより、不必要な紛争を防止し、スムーズに祭祀財産を承継することができます。
遺言書作成

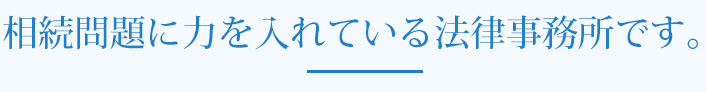
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

代表弁護士 金田 真明
![]()
東京都府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル3階
経歴
富山県高岡市出身。
慶應義塾大学法学部法律学科、関西学院大学司法研究科卒業。
司法修習修了後、東京都日本橋にある第一中央法律事務所で勤務。
同事務所では、企業の再生や労務問題等、企業にまつわる様々な業務に携わりました。
2011年1月11日に、あかつき府中法律事務所を設立
主な対応エリア
立川市/八王子市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/武蔵村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/
多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市/瑞穂町/日の出町/檜原村/奥多摩町の多摩地区/その他23区および神奈川県(南武線、小田急線沿線地域)埼玉県・山梨県など。
COPYRIGHT©あかつき府中法律事務所ALL RIGHTS RESERVED.